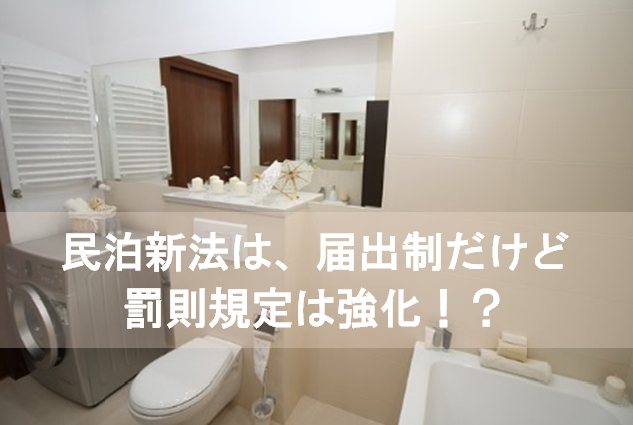建築物の敷地は道路に接していなければなりません。
当然ですよね。家から外に出ても、道路まで行けなかったら、コンビニへ買い物にもいけません。
「道路に接する」って、当たり前のことではないのでしょうか?
建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない(建築基準法第43条)
特殊な場合を除いて、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に2m以上接しなければいけません。
※法上「特殊建築物」とよばれるものには、接道幅について条例等で制限を受ける場合があります。この記事では住宅の敷地を前提としてはなしを進めます。
基本形は、これです。



Lが2m以上ならOKです。
①は、2m幅の土地というのも、ちょっとないかもしれませんが、基本OKです。
②は、よく「旗竿敷地」とよばれる形状です。l(小文字のエル)については、住宅なら問題になりませんが、用途によっては距離の制限がかかることがありますので注意して下さい。
③は、敷地と道路の間に、水路や川がある場合に橋を架けて道路につなげる場合です。この場合、確認申請の前に、「接道要件」を満たすことについて行政の許可(法43条の但し書きの許可といいます)が必要な場合があります。
(事前に水路等の管理組合の同意が必要な場合もありますので、こういったケースでは、細心の注意をはらって下さい。ただし、行政によっては、許可を必要としない場合もあります。)
2m接していても、建築物の敷地として認められない場合
下の3つは接道としては認められません。
①のようなケースは、あまり無いと思いますが、⑤と⑥のような場合は、気をつけてください。



袋地の場合の、「囲にょう地通行権」に対しては、確認申請は下りるのか?
囲にょう地という言葉を聞いたことがありますか。周囲を他人の土地に囲まれて道路に出れない土地のことをいいます。「袋地」とか「しに地」と呼んだりします。
民法上、こういった土地には「囲にょう地通行権」といって、道に出るために隣地の一部を通路として通行する権利が認められています。
(この権利は、登記が必要ですので注意して下さい。)
しかし、あくまで他人の土地です。自分の敷地は道路には接していません。
ただ、建築基準法上は、他人の土地でも確認申請は通りますので、①番のような敷地という考えでいけば、確認申請は通ります。
ただ現実的には、土地の権利関係が絡んでくる場合は無理しないほうが良いですね。
まとめ
少々レアなケースをお話しましたが、いかがでしょうか。
あくまで建築基準法上どうなのかということであって、工事のことや実際の生活のことは考慮していませんので、ご了承下さい。
道路に関しては、造成団地での新築の場合はまず問題になることはありません。
ただし、旧市街地や郊外の中古住宅を購入する場合などでは、道幅が狭かったり、公図上水路が残っていたりする場合もあって、建替え時に問題になることもありますので、十分注意して下さい。